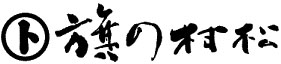のれん。暖簾 トロマット片面 防炎無しW1640xH1000 4割れ

店の入り口にかける暖簾。
伝統的なのれん生地の歴史は、少なくとも**平安時代(794年~1185年)には始まっています。最古の記録は絵巻物『信貴山縁起絵巻』で、当時の庶民が部屋の仕切りや風除け、雨除けとしてのれんを用いる様子が描かれています。
初期の生地には、麻がよく使用されていました。これは、日本最古の歴史書『日本書紀』にも神事用の麻布(青和幣・あおにぎて)が記載されていることや、繊維としての耐久性・通気性が理由とされています。ほかに綿や、のちの時代には帆布なども使われるようになりました。
鎌倉〜室町時代(12世紀以降)には染め抜きの技術が発達し、屋号や家紋を染めた印染めののれんが登場します。江戸時代には識字率向上とともに文字情報が入るなど、商家の看板や家業の象徴的役割も担うようになりました。
まとめると、のれん生地の歴史は日本の生活・商業風景とともに発展してきたもので、特に麻や綿などの植物繊維を主素材にした布地が伝統的とされています。

4人兄弟姉妹の3番目として、金沢市二俣町に生まれる。縁を頂き15代続く金沢の旧家に、婿養子として入る。(旧姓坂井)
リンゴが何よりの大好物で、リンゴ命のようなところがある。
学生の頃リンゴを食べすぎて、消毒の白い粉が芯の周りに残っているのに、早く食べたいという気持ちがはやり食べ過ぎて、農薬による病気になったことがある。
趣味は、薪ストーブに使うマキ割り!
人の寿命が120年説を唱え今が、青春真っ盛りの60歳台後半。折り返し地点を過ぎたところ。
皆様の喜んでいただけるようオーダー品の旗、幕、のぼり旗、暖簾、提灯、はっぴなどを製作させていただいています。
また、両面のぼり「表裏一体」を3年かけて作り皆様のご要望にお応えしています。
3.11大震災後は、津波フラッグなどの作成に携わっています。
旗でプライドを、手芸で愛を、お届けする!
を、理念に掲げ、お客様の喜んでいただけるお顔を思い浮かべながら仕事に取り組んでいます。
旗、幕、のぼり旗、提灯、はっぴ、横断幕、懸垂幕、(社旗、学校旗、幔幕、会旗)など、どんなことでもお問い合わせください。
また、ご予算、納期などございましたら、あらかじめ伝えていただいていますと助かります。
連絡先 080-3049-5155 村松(最速でお答えします。)
メール info@e-muramatsu.jp
住所 〒920-0902 金沢市尾張町1-11-12
電話番号 076-261-0165 ファックス 076-261-0169
(写真は、家族全員で先祖のお墓にお参りした写真2023.1.1)
※お問合せはお気軽に☆☆